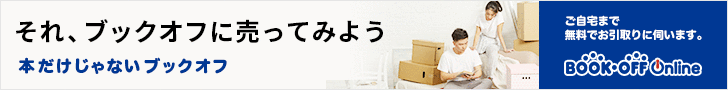原体験による経験は、結構後々までその人の趣向を左右すると言われますが、私は正にそんな感じの部類だと思っています。
何回か記してきましたが、音に関しては学生の頃、オーディオ店でのアルバイトがその原体験だったことは間違いないようです。
そこで出会ったアルテック 、そして620Bモニターの音は19歳の若者に相当なインパクトを与えたんだと思います。
それ以来、ほぼ45年間、ずっと一緒ですので、もはや熟年夫婦みたいなものです(笑)
その頃お店では、プリアンプはマッキントッシュC29、パワーアンプは同じくMC2205かMC2500、または管球式のミカエルソン&オースチンTVA-1が定番でした。
それらと組み合わせたときの620Bモニターの音は、とにかく良い音だと感じましたが、それはどこがどうとか、そういうことではない、もう感覚的に好きだ、としか言いようがなかったと思います。
いまなら少しは言語化できるような気がして、レビューとして追記しています。
それはなぜかと言いますと、仕事で使うモニタースピーカーを所謂音場補正して部屋の特性を含めてフラットにチューニングして、やっと信頼できる基準を得ることができたことがきっかけです。
それは、NEUMANNのパワードスピーカーに同じくNEUMANNのサブウーファーのシステムで、何回かの測定をしてDSP機構により実現できるものです。
今はレコーディング、音楽制作ではなんの迷いもなくその音を基準としていて、モニターコントローラーで3系統のスピーカーを切り替えが出来るようにしています。もう1組はGENELECを繋いでいて、それは極たまにNEUMANNから切り替えて比較用途で使用しています。
ALTEC 620B(当方はブラックバッフルの718A)はそのうちの1系統で、オーディオマニアの方からしますとかなり異質な組み合わせで、すなわちプリアンプ機能としてSSL(Solid State Logic)のSixというアナログミキサーから、パワーアンプCROWN DC-300A Series IIという80年代のスタジオでよく使われていた機材経由です。
そこに至る紆余曲折の経緯は、是非下段のエッセイコーナーでご笑読ください。
Bill EvansのWaltz For Debbyや最近ものでは(もはやそうでもないですが)Norah JonesのCome Away With Meをアナログレコードで聴く620Bの音は、一言で表すとしたら「実在感のある音」、とでも言いましょうか、リアリティ溢れる音なんですね。
その言語表現に対しても、人によっては様々な印象、それぞれ違った音世界があると思いますので、あくまでも私の拙い言い回しとなることは充分に承知しています。
音楽がそこにある、という感じがするという表現にもなります。
ここで、その状態から例のフラットに調教したNEUMANNに切り替えます。
一瞬で場が静かになり、全ての楽器の音がきれいに聴こえ、中域が引っ込んでいるように聴こえ、低域が25Hzくらいまでほぼフラットなのでどちらかというと低域よりのバランスに聴こえます。
最初は正直かなり違和感がありますが、しばらくすると慣れてきて、どう思うかと言いますと、「良い音だ」となり、そうか、こういう音なんだ、と納得してしまいます。
そしてその後、なんか物足りなくなってしまいます。
アルテック に切り替えます。
あ〜、やっぱりこれだ!となります。
オーディオ評論家的にもっと具体的に表現できれば良いと思いますが、結局はそういうことなんです(汗)
とはいえ、まだ言い切れていない気がしますのでまた追記していこうと思っています。
| ALTEC LANSING 620B / 718A Studio Monitor Speaker System |
|
| 再生周波数特性 | 20~20,000Hz |
| 許容入力(連続プログラム) | 65W |
| VCインピーダンス | 8Ω/400Hz |
| 出力音圧レベル(新JIS) | 103dB/400Hz |
| クロスオーバー周波数 | 1.5KHz |
| 外形寸法(H×W×Dmm) | 1,020×660×460 |
| 総重量 | 68.5Kg |
| ボックス | 620B / 718A |
| 使用ユニット | 604-8H デュプレックス |
| 最低共振周波数 | 30 Hz |
| 口径 LF | 15インチ |
| 口径 HF | 2.25インチ |
| マグネット LF(磁束密度) | アルニコV 13,000 gauss |
| マグネット HF(磁束密度) | アルニコV 15,500 gauss |
| ボイスコイル LF | 3インチ エッジワウンド コッパーリボン |
| ボイスコイル HF | 3/4インチ エッジワウンド アルミニュームリボン |
| ホーン | コンスタントダイレクティヴィティ マンタレイ 60°H × 40°V |
| バッフル開口径 | 35.9cm |
| ユニット外形寸法 | 40.6cm × 28.3cm |
| ユニット重量 | 15.4kg(ネットワーク含む) |
*718Aはバッフル面がブラック仕様で、本国では、MODEL 18の名称で販売された
(画像、仕様は当時の株式会社エレクトリ様カタログより)
ALTEC Products
<アルテックプロダクツ>
1.604 Series History & Spec
604の歴史と歴代仕様
2.ALTEC Series Around 1980
スピーカーシリーズ 1980年前後期
3.ALTEC System Around 1980
スピーカーシステム1980年前後期
4.ALTEC Component
スピーカーユニット
5.ALTEC 620B / 718A Monitor
620Bモニタースピーカー
6.ALTEC 620B Review
アルテック620Bレビュー
7.ALTEC Catalog
貴重なカタログからの掲載
ALTEC 604 Essay
<アルテック604のエッセイ>
1.アルテックとの出会い
2.アルテック604に臨む
3.Mclntosh MC2105
4.アルテック主将
5.SME 3012-R
6.marantz 3600 / 510M
7.Mclntosh C22 / MC240
8.marantz CD-94 Limited
9.marantz CDA-94 Limited
10.AUSTIN TVA-1
11.620Bセッティング
12.ケーブルのお話
13.AMCRON D-45
14.604-8Hユニット逆転
15.CROWN DC300A S II
16.KENWOOD L-07D
17.フォノイコライザー
18.P&G フェーダー
19.718Aモニター(604-8H)
20.アルテック604雑誌広告
ALTEC 604 Essay
<アルテック604のエッセイ>
1.アルテックとの出会い
2.アルテック604に臨む
3.Mclntosh MC2105
4.アルテック主将
5.SME 3012-R
6.marantz 3600 / 510M
7.Mclntosh C22 / MC240
8.marantz CD-94 Limited
9.marantz CDA-94 Limited
10.AUSTIN TVA-1
11.620Bセッティング
12.ケーブルのお話
13.AMCRON D-45
14.604-8Hユニット逆転
15.CROWN DC300A S II
16.KENWOOD L-07D
17.フォノイコライザー
18.P&G フェーダー
19.718Aモニター(604-8H)
20.アルテック604雑誌広告