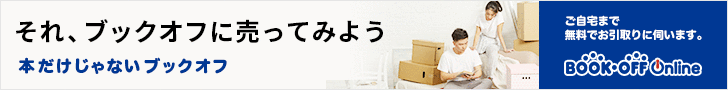ワイドレンジ化への対応期
1980年前後期のモデル

ドライバーにタンジェリンフェイズプラグと、新開発定指向性ホーンのマンタレイホーンを実装した604-8Hを搭載し、高音域を伸張。
さらに2Wayでありながら高域、中域を別々で調整できるデュアルバンドイコライザーを搭載。デュアルバンド時には中域の膨らみを抑えてフラット感を出すことができる一方、スイッチ切り替えで従来のレベル調整のみの場合は押し出しとリアリティが増す印象。
ブラック前面バッフルのモデル名は718A Monitor(本国ではModel 18)

604シリーズにおいてマルチセルラからマンタレーホーンに変わった最初のモデル且つ、最後のアルニコモデルが604-8H。
さらにオリジナル604-8Hのホーンのデットニング処理と620Bボックスのダクトチューニングを受けたカスタムモデルが620B CUSTOM。
おそらく鳴きを抑えてよりフラット感を出そうとしたのではと思われる。
エレクトリックギターの「フェンダー」に在籍していたポール・スプランガー氏のチューニングとなるモデル。
不思議なのは、オリジナル620Bシステムより価格が結構お安いこと。

当時、604-8Gのホーンを改造して搭載、ローエンド領域カバーに38cmのウーファーをプラス、さらにタイムアライメント重視のクロスオーバーを組み込んだ「Urei 813」がアメリカのレコーディングスタジオで猛威を振るっていた。
また、それ以前も低域に関しては同じようなコンセプトでオーディオテクニックス社の<ビッグ・レッド(BIG RED) システム>もスタジオの壁面に埋め込まれている写真が多く見られた。
要はALTEC604プラスサブウーファーという組合せ。
本国ではさすがにその対抗策は無理だったようだが、例によって日本のエレクトリはまたまたスゴイことをやってくれた。
基本的には、604-8Hをメインに下を416-8BSWを、上に6041-STを足す形でシステム化。
604-8Hのバックキャビティが小さいので604フリークとしては使い方に不満があったものの超弩級の鳴り方はもの凄いものがあった。
残念ながら6041-STスーパートゥイターは某メーカーのOEM製品。
その後、6041/IIとなりフェライト化された604-8KS搭載となる。

ホームユース A-7というコンセプトだと思われる構成で、それ以前も「マグニフィセント」という機種がやはり低域をショートホーンで2Wayの構成だった。
本来ならウーファーには416系なのだろうが、ここはロングストロークの411系とショートホーン&バスレフ。
ただ、どういう訳か416が搭載されてる写真もあったので、試作機だったのか、その辺りは定かではない。
802系のドライバープラスセクトラルホーンは定番としても、さらに上の帯域を902系ドライバープラスマンタレーホーンを追加した3Wayでまとめた。
ダイナミック感とレンジ感をうまく両立、相当完成度は高かった。
ドライバーは最初期に802-8G、以降フェライト化された902-8Aを使用。

どう見ても例のJBLの4343を意識して企画されたと思われる4Wayモデル。
上の9861もそうなのだが、ずっとエレクトリがALTECに要求を出していたのが「ワイドレンジ」だと言う。
12インチウーファー414と定番ドライバー802でファンダメンタルをしっかり押さえて上は950というスーパートゥイター、最低域は416のコーン紙に質量をもたせてローエンドを伸ばしたスペシャルユニットで構成。
レベル合わせが相当シビアなモデルだったけど、そのポテンシャルは凄まじいものがあった。
ただ、ユニットは全て本流ながらあまりにもALTECらしくないまとめ方だった。
ずっと後で解ったことだが、ミッドのホーンと、スーパートゥイターともしっかりとALTECの作だった。
また、発売当時はアルニコ、後期にはフェライトに移行、バッフル面のカラーもアルテックグリーン又はブラックの違いがあった。
本国アメリカでもかなりレアらしく、ネット上で話題になったり、実は「日本のオークションで落札して欲しい」というメールが海外から数件来たりした。
画像は株式会社エレクトリ様と本国の、当時のカタログから掲載させていただきました。
Images are posted from the catalogs of ERECTORI Co., Ltd. and the home country at the time.
ALTEC Products
<アルテックプロダクツ>
1.604 Series History & Spec
604の歴史と歴代仕様
2.ALTEC Series Around 1980
スピーカーシリーズ 1980年前後期
3.ALTEC System Around 1980
スピーカーシステム1980年前後期
4.ALTEC Component
スピーカーユニット
5.ALTEC 620B / 718A Monitor
620Bモニタースピーカー
6.ALTEC Catalog
貴重なカタログからの掲載
ALTEC 604 Essay
<アルテック604のエッセイ>
1.アルテックとの出会い
2.アルテック604に臨む
3.Mclntosh MC2105
4.アルテック主将
5.SME 3012-R
6.marantz 3600 / 510M
7.Mclntosh C22 / MC240
8.marantz CD-94 Limited
9.marantz CDA-94 Limited
10.AUSTIN TVA-1
11.620Bセッティング
12.ケーブルのお話
13.AMCRON D-45
14.604-8Hユニット逆転
15.CROWN DC300A S II
16.KENWOOD L-07D
17.フォノイコライザー
18.P&G フェーダー
19.718Aモニター(604-8H)
20.アルテック604雑誌広告
ALTEC 604 Essay
<アルテック604のエッセイ>
1.アルテックとの出会い
2.アルテック604に臨む
3.Mclntosh MC2105
4.アルテック主将
5.SME 3012-R
6.marantz 3600 / 510M
7.Mclntosh C22 / MC240
8.marantz CD-94 Limited
9.marantz CDA-94 Limited
10.AUSTIN TVA-1
11.620Bセッティング
12.ケーブルのお話
13.AMCRON D-45
14.604-8Hユニット逆転
15.CROWN DC300A S II
16.KENWOOD L-07D
17.フォノイコライザー
18.P&G フェーダー
19.718Aモニター(604-8H)
20.アルテック604雑誌広告