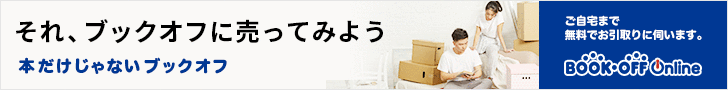アルテック604シリーズの原型となる最初の同軸型スピーカー「601」の発表が1943年、12 インチの601同軸型スピーカーは多くの有名なアルテック・ランシングのデュプレックス同軸スピーカーの最初の製品となりました。
1945年、世界中で最も著名で、最もプロの現場での実績を上げる同軸型スピーカー604シリーズの初代が登場します。
元々、潜水艦のソナー用のスピーカーユニットとして開発され、1944年には完成しましたが、第二次世界大戦には間に合わなかったとあります。
ご存知の方も多いと思いますが、開発は当時アルテック に在籍していたジム・ランシング氏(JBLの創始者)で、さらには604のウーファーをベースとし、まもなく基幹ウーファーの515が誕生しますが、515は氏に敬意を表しユニット裏側マグネット部に「Lansing」の銘板をつけたと言われています。
低域、高域それぞれ独立したマグネットを使用し、ウーファーの中を貫通したホーンから高域を放射するという非常に贅沢な、ある意味理想的な構造。
幅広い周波数のカバーと、広大なダイナミックレンジ、そしてなによりもこの方式の最大のメリット、点音源による群を抜く定位感がその後の絶大なる信頼感の源と なったことは改めて言うまでもありません。
圧倒的な能率の高さから来る実在感と、リアリティー、それは他の追随を許さないサウンドに昇華したと言えます。
そして、アルテックはこの独自の同軸構造のユニットを「デュプレックス」(Duplex) シリーズと総称していました。
その後も604シリーズは幾度の改良がインプットされて常に時代の要求を越える仕様を発表してきました。
特に駆動するアンプが真空管からトランジスターへと変化するのに合わせたインピーダンスの16Ωから8Ωへの変更、フィックストエッジからフリーエッジへ の改良による耐入力の向上、アルニコの最終期においてはタンジェンシャルフェーズプラグを導入し、ハイエンドの伸びを一気に加速し、また、長年その顔となっていたセクトラルホーンを定指向性のマンタレーホーンへ変更、ここでレンジの拡大と透明感を付加された音が完結。
どちらかと言うと大味だったと言われる音に繊細感も付加されました。
その後世界的コバルトの高騰によりアルニコからフェライトへのマグネットの変更により奥行きが浅くなる関係でホーン長を短くする必要から、大幅な構造変更が大きなトピックスとなりました。
初めて東京中野サンプラザに行った時、あまりにも場内アナウンスがきれいで素敵な声なのにびっくりしました。
それがアルテックの604からのものだと知ったのはずっと後でしたが、まるっこい球体がステージの上方にいくつもあったのを今でも覚えています。
その他にも武道館、宝塚大劇場、大阪飛天劇場などには数十台の604が使用されていたとのことです。
もっともその主たるはレコーディングスタジオあるいはラジオ局、映像関連のモニターユースと言うのは周知の通りですが、1973年のビルボード誌調査においてはアル テックランシングのスピーカーシステムは「レコーディングスタジオ」で他を圧倒し一番多く使われているという結果が発表されたりしました。
一方、時代とともにいくつかの問題点も指摘されるようになりました。
一つは、604の音質の特徴でもあった中域の張り出しをもっと平坦化したいというニーズで、マスタリングラボ社は独自のクロスオーバーを開発、フラット指向の流れにマッチしたようで、オーディオニックス社はこのクロスオーバーを使用し、604Eのユニットと組み合わせビッグ・レッドモニターを開発、1970年代にスタジオユースでかなり使われたといいます。また、音楽自体のトレンドは低域をかなり重視する傾向にあり、さらにウーファーを追加したモデルも投入され、スタジオコントロールルームやブースで壁面に埋め込まれた写真を見ることがありました。
もう少し新しいところでは、UREI社が604-8Gを使用しタイムアライメントをとることができるシステムを開発し、位相ズレの問題を解決、1977年ころ813モニターとしてリリースしました。ブルーのホーンに換装され、サブウーファーを搭載していて、そのウーファーが上、604が下、というユニークなデザインでも話題になりました。813、813Aまでが604を使用、その後の813BではPAS社製ウーファーにJBLのドライバー&ホーンを採用したユニットとなりました。どうやら604の供給不足も一因だったようです。
上記のように、70年代から「604プラスサブウーファー」という時代の流れがあったにもかかわらず、本国のアルテックはなかなかその方向には動かないと判断した当時の輸入元エレクトリは、604-8H時代に6041というモデルを開発、リリースしました。サブウーファーに416の改良型(416-8BSW)を採用し、さらにスーパーツイーター(こちらは某社のOEM品)を追加した4ウエイという超弩級システムでした。今更ながら、すごいことをやってのけたと感心します。
さて、モニタースピーカーといいますと検聴用、検証用ひいてはあら探し用などとネガティブなイメージもあるかもしれませんが、このアルテックの名機604シリーズ に関してはプラスしてその音楽性の豊かさ、「楽器の音」がするとしてミュージシャンや、特に耳が良いとされる日本のオーディオファイルを中心としてプロ ユース以外にも絶大な人気を誇りました。
オールド、ヴィンテージファンの中では昔の604が最高だと言う方が沢山いらっしゃいます。
実際現在でも初代からB,C,Dはかなり高額で取引されていますし、その豊潤でコクのあるアルテックトーンはシンプルで高品位な真空管アンプでこそ活かされるとされています。また、実際のスタジオユースにおいてはE~Gが全盛期だったと思われます。この辺りの詳しい比較につきましては、管球王国No.25アルテック604研究、または、別冊ステレオサウンドALTECでご覧いただけます。
1978年、アルニコ最終モデル604-8Hに於いてはタンジェリンフェイズプラグの実装、マンタレイホーンへの換装、デュアルバンドイコライザーの採用等、技術の総力が結集されたバージョンとして、その名が残る仕様となりました。
>> 604-8H/620Bモニターの詳しい情報はこちらのページへどうぞ!
その後、世界的なコバルト不足からアルテックとしてもマグネットをアルニコからフェライトへ変更する必要に迫られ、ホーン長の縮小等大幅な構造変更を施し、604の実質的最終モデル604-8Kが登場します。
アルテックとしては、ごく当たり前ではありますが「その時」の604が最高と言い続け、日本のミスターアルテック森本さん曰く「最終の604-8Kにおいては604-8H の特徴を全て備え、且つ繊細感を加えて大幅に性能向上を果たし、従来モデルよりも遙かに好きなサウンドだ」と仰っています。
株式会社イーブイアイオーディオジャパンからは、その604-8Kユニットに1.6kHzクロスの独自ネットワークを組み合わせた「Milestone 604」が一時期発売されました。クロスオーバー周波数帯域の中音域のみ可変できるタイプだったようです。
この前後で長年国内にアルテックを導入、貢献してきたエレクトリから輸入元が変わったのだと思われます。
その後、2002年に604-8Lという型番が誕生し、国内では株式会社バラッドより「Ba620」というモデル名で発売されていました。ユニット自体は8Kとほとんど変わらない仕様かと思われますが、マスタリングラボ社のクロスオーバーを採用して、604-8Kよりさらに滑らかな周波数特性を実現しました。
そして驚くべきことに、GPA社より、「604-8H-II」が市場に出されました。
ALTECの天才エンジニアと言われたビル・ハニャック氏は、最終モデルである604-8K及び8Lには満足していなく、史上最高の604を作りだそうとALTECの他のエンジニア達も引き連れてGPA(グレートプレインズオーディオ)を興しました。
彼らのなかではやはり、既に604-8Hで完成されたという意識と、それが過去最高の音だという認識で、フェライトでもここまで出来るというエンジニア魂をその型番「604-8H-II」で表現したかったそうです。
長年604-8Hを愛用してきた私としましては大変嬉しく思う次第です。
さらに2009年、その604-8H-IIは改良されて604-8H-IIIへと進化しました。
その「顔」であったマンタレーホーンががらりと変化し、8Gまでのマルチセルラタイプの大きさにまで小型化してます。
国内では株式会社バラッドが、それらのユニットを採用し、トールボーイ型230リットルのエンクロージャーに組み込み、Ba604H-IIという名称でシステム化して販売していました。
Ba604H-II Trial listening
現在でも、歴代の604シリーズは専門誌等での試聴用ユニットとしてその活躍を見る事があります。
また、近年は中国における富裕層の間で、かなり活発な取引がされているとも言われています。
また、最近ウィキペディアで発見したのですが、2005年にアルテック 604デュプレックスシリーズはテクノロジーの殿堂入りをしたとの記述があり、そのサイトはかろうじて残っていましたのでリンクを貼っておきます。
The significance of the Duplex loudspeakers is evidenced by the fact that the Altec Lansing 604 Duplex was inducted into the TECnology Hall of Fame in 2005.
the NAMM TEC Awards
アルテック604シリーズ歴代の仕様、諸元、情報は、別冊ステレオサウンド誌 ALTEC、サウンド与太噺(森本雅記様記)、当時の輸入元カタログ、本国カタログ等の引用を含めご案内させていただきました。
画像は株式会社エレクトリ様と本国の、当時のカタログから掲載させていただきました。
Images are posted from the catalogs of ERECTORI Co., Ltd. and the home country at the time.
| ALTEC 604 Duplex Series All Models Spec |
|||||||||||||
| model | release | impedance | crossover | fo | sensitivity | frequency responce |
power handling capacity |
magnetic flux density LF |
magnetic flux density HF |
magnet | edge | horn | etc. |
| name | year | Ω | Hz | Hz | dB | Hz | W | gauss | gauss | ||||
| 604 | 1945 | 20 | 2,000 | 38 | - | 60~15,000 | 25 | - | - | ALNICO V | fixed | multicellular | ※3 |
| 604B | 1948 | 16 | 1,000 | - | - | 30~16,000 | 30 | - | - | ALNICO V | fixed | multicellular | |
| 604C | 1952 | 16 | 1,600 | 40 | - | 30~20,000 | 35 | 13,000 | 15,500 | ALNICO V | fixed/free | multicellular | |
| 604D | 1957 | 16 | 1,600 | 40 | - | 30~22,000 | 35 | 13,000 | 15,500 | ALNICO V | free-edge | multicellular | |
| 604E | 1967 | 8~16 | 1,500 | 25 | 101 | 20~22,000 | 35 | 13,000 | 15,500 | ALNICO V | free-edge | multicellular | |
| 604-8G | 1975 | 8 | 1,500 | 30 | 103 | 20~22,000 | 40 | 13,000 | 15,500 | ALNICO V | free-edge | multicellular | |
| 604-HPLN | 1978 | LF 8/HF 16 | 1,500 | 34 | LF 97/HF 105 | 50~20,000 | 80/15 | - | - | ALNICO V | free-edge | multicellular | ※4 |
| 604-8H | 1978 | 8 | 1,500 | 30 | 103 | 20~20,000 | 65 | 13,000 | 15,500 | ALNICO V | free-edge | mantaray | ※5 |
| 904-8A ※1 | 1980 | 8 | 1,500 | - | 102 | 60~20,000 | 125 | - | - | FERRITE | free-edge | mantaray | ※6 |
| 604-16X | not clear | LF 16/HF 16 | 1,500 or higher |
30 | LF 101/HF 107 | 50~20,000 | 100/10 | 13,000 | 15,500 | FERRITE | free-edge | mantaray | |
| 604-168X | not clear | LF 8/HF 16 | 1,500 or higher | 30 | LF 101/HF 107 | 50~20,000 | 100/10 | 13,000 | 15,500 | FERRITE | free-edge | mantaray | |
| 604-8K | 1981 | 8 | 1,500 | 24 | 98.5 | 20~20,000 | 75 | 13,000 | 16,000 | FERRITE | free-edge | mantaray | ※5 |
| 604-8L | 2002 | 8 | 1,500 | 24 | 98.5 | 40~20,000 | 75 | 13,000 | 16,000 | FERRITE | free-edge | mantaray | ※5 |
| 604-8H-II ※2 | 2006 | 8 | 1,500 | 30.9 | 99 | 30~20,000 | 100 | 12,800 | 17,000 | FERRITE | free-edge | mantaray | ※7 |
| 604-8H-III ※2 | 2009 | 8 | 1,500 | 33.7 | - | 40~20,000 | 100 | 13,000 | 16,000 | FERRITE | free-edge | radial | ※7 |
■ 資料及び参考にさせていただいた文献等・・・別冊ステレオサウンドALTEC、サウンド与太噺(森本雅記様記)、当時の輸入元カタログ、本国カタログ
ALTEC Products
<アルテックプロダクツ>
1.604 Series History & Spec
604の歴史と歴代仕様
2.ALTEC Series Around 1980
スピーカーシリーズ 1980年前後期
3.ALTEC System Around 1980
スピーカーシステム1980年前後期
4.ALTEC Component
スピーカーユニット
5.ALTEC 620B / 718A Monitor
620Bモニタースピーカー
6.ALTEC Catalog
貴重なカタログからの掲載
ALTEC 604 Essay
<アルテック604のエッセイ>
1.アルテックとの出会い
2.アルテック604に臨む
3.Mclntosh MC2105
4.アルテック主将
5.SME 3012-R
6.marantz 3600 / 510M
7.Mclntosh C22 / MC240
8.marantz CD-94 Limited
9.marantz CDA-94 Limited
10.AUSTIN TVA-1
11.620Bセッティング
12.ケーブルのお話
13.AMCRON D-45
14.604-8Hユニット逆転
15.CROWN DC300A S II
16.KENWOOD L-07D
17.フォノイコライザー
18.P&G フェーダー
19.718Aモニター(604-8H)
20.アルテック604雑誌広告
ALTEC 604 Essay
<アルテック604のエッセイ>
1.アルテックとの出会い
2.アルテック604に臨む
3.Mclntosh MC2105
4.アルテック主将
5.SME 3012-R
6.marantz 3600 / 510M
7.Mclntosh C22 / MC240
8.marantz CD-94 Limited
9.marantz CDA-94 Limited
10.AUSTIN TVA-1
11.620Bセッティング
12.ケーブルのお話
13.AMCRON D-45
14.604-8Hユニット逆転
15.CROWN DC300A S II
16.KENWOOD L-07D
17.フォノイコライザー
18.P&G フェーダー
19.718Aモニター(604-8H)
20.アルテック604雑誌広告