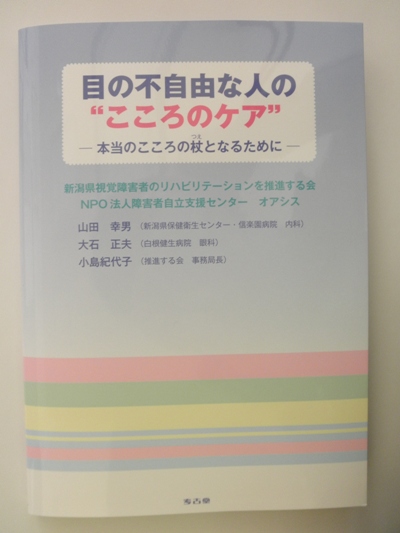
目の不自由な人の“こころのケア”
―本当のこころの杖となるために―
私たちが視覚障害者のリハビリテーションを始めたきっかけは、一人の目の不自由な人の自殺です。
35歳の失明男性A君で、目の不自由なことが原因で入院治療中の1984年に自ら命を絶ってしまいました。
彼の死を無駄にできないと考え、10年間の準備のあと、1994年5月に信楽園病院に「視覚障害リハビリテーション外来」を開設しました。しかしその甲斐もなく、開設4ヵ月後に目のリハビリテーションのために入院した女性失明患者Bさんも自殺を企て、亡くなってしまいました。
同じころ、1型糖尿病で失明したCさんも、命はとりとめたものの、入院するたびに自殺を試み、今でもあのときに死なせてほしかったと訴えます。
その後の調査で明らかになったことですが、目が不自由になるとそれが原因で、少なくとも2人に1人は死ぬことを考えます。いや、「目が不自由になると、誰もが一度は死ぬことを考える」といった方が正しいのかも知れません。
パソコンや携帯電話など文字を頻繁に使う現在のような情報社会にあっては、目が不自由になると、仕事や日常生活が難しくなります。
視覚障害者は生活行動や精神面で大きなハンディキャップを抱えながら、回復の見込みがないままに、生き続けなければなりません。
視力の残っている人は、全く見えなくなるのではないかと、不安を抱きながらです。
がんなどの病気と違って、視覚障害の終点には“死”がありません。だから、耐えきれなくなると、自分から死を選ぶのだと思います。
目の不自由な人には、白杖歩行や点字の技術を身につける前に、こころのケアが必要です。
そのため私たちは同じ病気を持つ人やスタッフ、ボランティアさんと気楽にお茶を飲みながら話のできる場を1995年5月に開設しました。
「パソコン教室 オアシス」です。
そこは、こころの相談室であり、また音声パソコンや点字、拡大読書器の使い方を学ぶ教室、さらに、おしゃべりなどをしてくつろぐ喫茶室です。
パソコン教室オアシスを開設して4〜5年たつと、自殺を企てる人はなくなり、自殺を考える人も減少しました。若い人たちは職に就くことさえ考えるようになりました。
化粧、調理、運動教室が加わってからは目の不自由な人たちの間には笑いが多くなり、「このような施設をもうすこし早くつくってもらっていたら、だれも死なないですんだのでは」という声が聞かれるようになりました。
目の不自由な人の治療は、こころのケアから始まります。
目の不自由な人を抱えた家族にも、目の不自由な人と同じくらいに、こころのケアは必要です。
無念にも自ら命を絶ったA君やBさん、また命は残ったものの苦しみ続けるCさんのためにも、私たちの体験をまとめて世に出すことが大切と考えました。本書が目の不自由な人たちのこころを楽にし、死ぬことを考える人が少なくなることに役立つことを願っています。